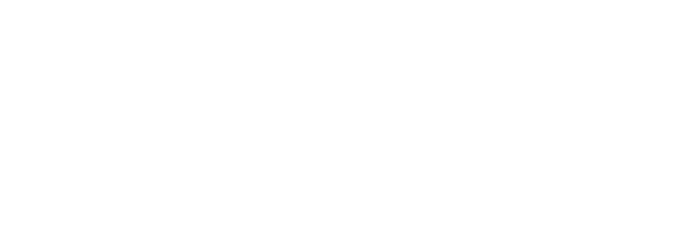- ja Change Region
- Global Site
- ホーム
- 製品・サービス
- 共焦点・多光子励起顕微鏡
- AX / AX R with NSPARC
Glial cell surrounded by axons in a rat neuronal culture labeled for microtubules and actin
Dr. Christophe Leterrier, NeuroCyto, INP, Marseille, France
インタビュー
開発・企画インタビュー 美しい画像のその先へ。AX/AX Rのパフォーマンスを最大化する、超解像共焦点レーザー顕微鏡システム AX/AX R with NSPARC
AX/AX Rに外付けするだけで、かつてない解像度での超高速スキャンにより、従来の共焦点レーザー顕微鏡では目にすることのできない生細胞のわずかな変化も観察・撮影できるNSPARC(エヌスパーク)。さらなる高みを目指した挑戦を、開発者が語ります。

NSPARCはどのようなコンセプトで開発されたのでしょうか。
ヘルスケア事業部
技術統括部
システム開発部 開発プロジェクト推進課
友杉 亘
友杉:『美しい画像のその先に、分子生物学や細胞生物学の新しい知見を得られる画像を提供する』。私たちの実現したい姿はここにあります。重視していたのは、AXのもともとの開発コンセプトでもある「拡張性」です。その拡張性に着目してAXの分解能をさらに高めることを目指しました。観察対象となるサンプルに制限をなくし、あらゆるサンプルを高い分解能で観察する環境を提供したい。その思いからNSPARCの開発に至りました。
ヘルスケア事業部
技術統括部
システム開発部 第一開発課
大川 潤也
大川:さらに共焦点レーザー顕微鏡は、研究で使用される実験器具の中でも中心的な役割を担うものです。だからこそ、初心者の方からプロフェッショナルまで、少しでも使いやすい操作感やGUI、ワークフローを提供して、研究の現場で気軽に活用いただきたいという思いもありました。
コアとなっているのはどんな技術でしょうか。
友杉:NSPARCは、IIT(イタリア技術研究所:Istituto Italiano di Tecnologia)内のニコンイメージングセンター(NIC@IIT)、分子顕微鏡法および分光法ラボ(MMS)で共同研究して得られた技術を活用しています。特徴的なのは、心臓部であるSPPC(Single pixel photon counter)アレイディテクターと呼ばれる特殊な検出器を採用している点です。この検出器には、SPPCと呼ばれるフォトカウンティングが可能な素子が2次元に25個配列されており、それぞれが小さなピンホールの役割を担うことで高い分解能の画像を得ることが可能となります。そこに特別な画像処理を加えることで、高い分解能でかつ明るい画像を得られるというわけです。
蛍光がSPPCアレイディテクターに、1エアリーユニット径のスポットサイズで内接するように投影されます。
蛍光はサイズが可変のピンホール(通常は1エアリーユニット)を通ります。
開発ではどんな苦労があったのでしょうか。
友杉:開発が進むにつれて、これまで見たことのないような高い分解能の画像が撮れるということが分かってきました。しかし、常にベストパフォーマンスを得るためにはSPPCアレイディテクターのど真ん中に、検出光の中心を入れ込む必要があります。光軸のズレに対して、どのようなアルゴリズムで光軸の補正をかけるか。評価を重ねて得られた知見を総動員して、より繊細でロバスト性の高い補正を目指し、チームメンバー全員で頭を悩ませながら取り組みました。
大川:そうですね。従来の顕微鏡よりも、アライメントの精度により精密さが求められる製品ですので、非常に大変でした。しかも共焦点レーザー顕微鏡は、パラメーターが多岐にわたります。ですから、ひとつひとつの仕様を整理するという点にも苦心しましたね。
NSPARCで撮影したミトコンドリアのライブセルイメージング
画像ご協力:Center for Biologic Imaging, University of Pittsburgh
友杉:最終的には、お客さまが触るパラメーターは、極力少なくするというのが理想であると考えます。実際、1mmの半分にも満たない極小の検出器の真ん中に検出光が当たるように光軸を調整することで、明るさ、分解能のベストパフォーマンスが得られます。そのため、工場組み立て時やセットアップ時の調整方法、工具、ソフトウェアの検討にもかなりの時間を費やしました。
社内ソフトウェアでさまざまな条件のもと、幾度も検出光の状況を確認し、結果としてハード、ソフトウェアの最適解を導きだせたと思います。撮影条件等に依存する数十umレベルの光軸のズレを簡単に調整できるよう、ソフトウェアにオートアライメント機能を実装しました。ここにお客さまが安心して、常にベストパフォーマンスで使っていただくための技術的なポイントが盛り込まれているかと思います。
大川:その最大のパフォーマンスを引き出すことと、いかにパラメーターを少なく簡単に使えるようにするかという、バランスのせめぎ合いもありますよね。ユーザーインターフェースやソフトウェアの仕様でも、いくつもの研究機関を訪問して実際の実験を見せていただき、ニーズを収集するところからのスタートでしたから。
友杉:使い勝手とベストパフォーマンスがトレードオフであってはならないですよね。バランスをしっかりと考えたところも苦労した点、工夫した点であったと思います。光学、メカ、電気、ソフトウェアと、あらゆる分野の知識と技術を結集させて、NSPARCシステムは完成にたどり着いたと言えます。
超解像顕微鏡というと、少し敷居が高いと感じてしまうところがあると思いますが、その複雑さを意識させないっていうところも大切ですよね。
大川:そうですね。従来の共焦点レーザー顕微鏡と、ほとんど変わらない使い勝手というところを目指していましたから。「普段使いの超解像顕微鏡」という感じで気軽に使ってもらいたい、というのが開発者の思いではありますね。
NSPARCが今後拓く世界への期待も高まりますね。
友杉:NSPARCを通して、新しい生命現象の知見を得ていただくことで、社会に貢献していきたいと考えています。まずは見慣れたサンプルで一度、観察してみてください。これまで気付かなかった新しい生命現象や自然現象が見られるかもしれません。
大川:これまで皆さまが見ていたサンプルをNSPARCで観察することによって、新しい生物学的な発見ができることを願っています。普段見ていたサンプルでも空間分解能を上げることで新しい現象が見える事例はたくさん出てくると思います。さらに、生物学的な発見が創薬や病気のメカニズムの解明につながると、とてもうれしいです。