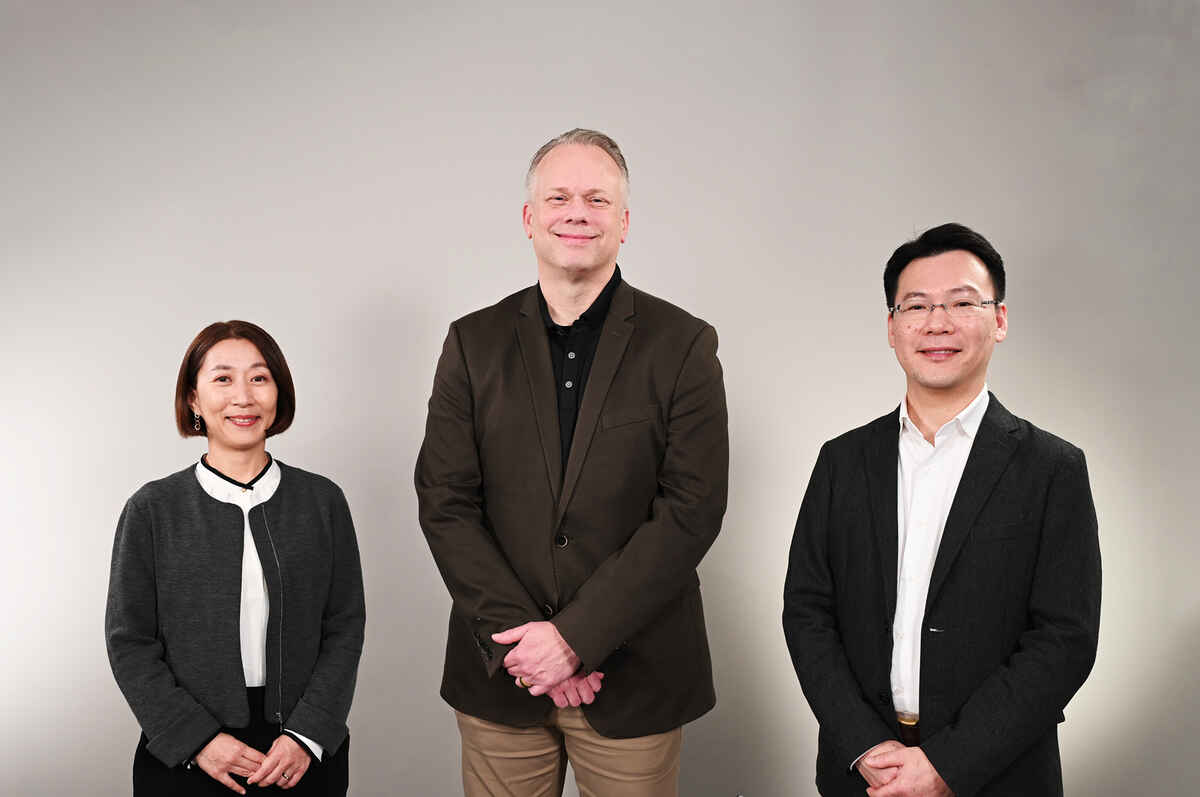中田: 対象ユーザーを従来の顕微鏡に習熟した方たちだけでなく、顕微鏡画像を用いた生物系の研究・業務に携わる幅広い層とし、開発のコンセプトを「簡単操作」、「実験効率の向上」、「システムのフレキシビリティ」としました。最初の「簡単操作」に関しては、顕微鏡の操作や最適化が難しいという、これまでの課題を解決するためのものです。次の「実験効率の向上」は、近年顕微鏡による画像情報の定量化と解析がますます重要になっている傾向に対して、設定の最適化から定量化・解析までのワークフロー全体を効率化するソリューションを提案したいと考えました。そして「システムのフレキシビリティ」については、研究トレンドや対象サンプルの変化、多様性にも柔軟に対応できるシステムを実現する必要があると考えたことが起点となっています。
ヘルスケア事業部
中田 千枝子
Davis : ここ数年、米国のマーケットにおける顕微鏡ユーザーの変化を実感していました。それは、皆さんが顕微鏡技術の理解や操作を習得するための時間を十分に得られていないことです。背景は、顕微鏡観察技術の複雑化、高度化や顕微鏡自体の高性能・高機能化などがありますが、これらをしっかり理解・習得していないと、データ収集の質が低下する要因となります。この課題を解決するために、顕微鏡の専門知識や経験が十分でなくとも、質の高いデータ収集を可能にするユーザー支援型の「スマート顕微鏡」を開発することが大きな目標でした。また、ベテランの顕微鏡ユーザー向けに、コアとなる機能とフレキシビリティを維持することも重要課題としました。
Nikon Instruments Inc. (USA)
Mike Davis
野中: 私の役割は、中田さんとマイクさんが立案したコンセプトを具現化することでした。先ほどの3つのコンセプトで、私が最も重要だと思うものは「簡単操作」です。従来の顕微鏡は結果を得るまでに複雑なハードウェアやソフトウェアの操作が少なくありませんでした。しかし、創薬や再生医療などの技術革新はめざましく、それにともない研究や業務の量やスピードも増していく傾向にあります。一方で働き方の改革やタイムパフォーマンス、個人の生活の質が意識される時代でもあります。そこで、「スマートフォンのアプリを使うように、簡単に顕微鏡を使えないか」というテーマに取り組みました。
ヘルスケア事業部
野中 崇雄
中田: ECLIPSE Jiの開発コンセプトを国内の各部署、さらに海外の拠点にも共有し製品化につなげていきました。デジタルトランスフォーメーション、デジタルネイティブ世代を見据えた顕微鏡のあるべき姿については、マイクさんを中心とするアメリカのチームからの提案をいただき大いに触発されました。そして製品開発の前工程・後工程のさまざまな方々と、前例のなかった早期の段階から議論や検討を進めていきました。たとえば、装置の自律的な判断と駆動のために、ソフトウェア、ハードウェアの開発チームと実現手段を模索。また、AIを活用した学習済みモデルのために、研究開発部門とも要素開発を進めました。さらに今回はサンプルの画像定量評価の結果までを製品の機能としたため、品証部門とも品質の検証方法を策定しました。
Davis : 初期のコンセプトの共有から最終的な製品化にいたるまで、ECLIPSE Jiの開発は常に、ワールドワイドな共同作業で進められました。私たちのアメリカチームは実際にユーザーが顕微鏡をどのように使っているのかを調査し、主要な課題がどこにあるかを抽出していきました。そして日本はもちろん、ヨーロッパも含む各国のメンバーが共有されたコンセプトの実現を目指して、検討と改良を繰り返していきました。最高性能の光学技術を駆使し、自動化されたシステムを完成させるには、多くの才能ある開発者と検証者が必要ですが、ニコンには優秀な人材と高いモチベーションがありました。
野中: このプロジェクトには、組織の枠を越えてさまざまな世代の技術者が関わっていました。たとえばハードウェア開発には経験豊富な設計者たち、ソフトウェア開発には、若い設計者たちが参加していました。これまでのニコンにはなかった新しいコンセプトの製品であったため、初めのうちはコンセプトの解釈も皆の認識が異なっており、それを製品の一つひとつの機能に落としていくことは非常に困難でした。しかし何度も議論を重ねていくうちに、共通の認識が生まれ、その過程に楽しさを感じました。また製品仕様を決める段階ではマイクさんを始めとした、国内外の販社の方たちからたくさんの意見をいただきました。今のJiには実装されていない機能もありますが、それらは今後のアップデートで順次実装していく予定です。
Davis : ライブイメージングでは時間が重要です。フォーカシングや適正露光、照明の設定などに迷うとサンプルの状態に大きく影響します。AIを介して顕微鏡自体にこれらのプロセスを学習させ、サンプルの損傷を最小限に抑えることをECLIPSE Jiは目指しました。顕微鏡に関して30年以上の経験を持つ私にとって、これは非常にエキサイティングな出来事です。優れた光学技術と AI を融合することで、長い歴史を持つ顕微鏡が突然、より強力で使いやすいツールに進化したのです。そこには、何百年も続いてきた伝統的な外観も複雑な操作も存在しません。ECLIPSE Jiはさらにより高度なサポートを可能にするための進化を続けています。私はその可能性にとてもわくわくしています。
野中: 今回開発したECLIPSE Jiが創薬など多くの研究に役立つことを願っています。Jiを使えば顕微鏡に関連する複雑な操作やデータ解析にかける時間を以前よりも短くすることができます。そうして生まれた時間は、新しい研究に取り組んだり論文を読んだりあるいは公園を散歩したりといったことに使うことができるでしょう。そうして、広い意味で社会全体が豊かになっていくひとつのきっかけになってくれると嬉しいですね。ヒアリングをさせていただいたユーザーの皆さまも含めて、ECLIPSE Jiの開発に関わったすべての皆さんに感謝します。
中田: ECLIPSE Jiはサンプルのセッティングが簡単で即座に顕微鏡画像や定量の結果が得られるため、あらゆるライフサイエンスの現場でより気軽に使っていただければと思います。これによって対象サンプルの傾向把握、仮説の設定や修正、次の実験計画の策定などのアジリティが向上し、それらが新たな成果や発見につながることを期待しています。さらに、実験効率の向上が働き方改革やコスト低減にも貢献するでしょう。今後の課題ですが、ユーザーの方々や販売部門のスタッフからもさまざまな要望を伺っています。皆さんとともに次の課題に取り組み、新たなソリューションを協創していきたいと考えています。
*所属および掲載内容は取材当時のものです。